ネクスDSDジャパンニューズレター20230825
- nexdsdJAPAN
- 2023年8月27日
- 読了時間: 4分
ネクスDSDジャパン更新情報

ターナー症候群とは,女性のDSDs:体の性の様々な発達のひとつです。
一般的には女性はXXの染色体ですが,ターナー症候群の女性は染色体がXの1つ(45,X)で女性に生まれ育ちます。卵巣の機能不全による女性二次性徴不全や不妊状態,低身長,そしてセリアック病や甲状腺の病気など,様々な症状が現れることがあります。
医療では今では笑い話でしかありませんが,日本では今でもコミックなどの影響で,ターナー症候群の女性たちを「男でも女でもない両性具有」「男性化する」という誤解・偏見を持っている人もいます。
そして現在の日本では,非認定施設での新型出生前検査(NIPT)で,生まれる前にターナー症候群の疑いがかけられることも。この場合,ターナー症候群の女の子の胎児の人工妊娠中絶率は85%とも言われています…。
ですが,ターナー症候群の女性たちは,様々な誤解・偏見,そして様々な付随症状がありながらも,自分自身の人生と生活を精一杯生きていらっしゃいます。
イギリスのターナー症候群サポートグループから許可をいただき,ターナー女性のみなさんのライフストーリーを翻訳して公開しました。
ぜひご覧下さい!
ご存知でしたか?
現在の医療では笑い話でしかありませんが,実はターナー症候群の女の子・女性たちは,1960年からしばらくの間,まるで「男でも女でもない」「中性」であるかのように言われていました。
下の画像は,「性同一性(gender identity)」という概念を提唱した心理学者ロバート・ストラ-の1968年の著作の引用ですが,この心理学者が最初に「性同一性」という概念をDSDsに当てはめたのは、ターナー症候群(45,X)の女性に対してなのです。

ターナー症候群の女の子・女性たちはただの女性(female)であるにもかかわらず,「人間として許される範囲の,生物学的に中性状態」「生物学的には中性 」「自分の性が発生学的にも解剖学的にもまちがっている」など,染色体がXひとつであることや,女性二次性徴不全があるというだけで本当に酷い捉え方でした。。
このようなひどい捉え方になったのは,生物学者等による1960年のデンバー会議で,X・Y染色体が「性染色体」と呼ばれるようになってからです。この時から,「女性(female)は絶対XX,男性(male)は絶対XY」という「社会的生物学固定観念」が強迫的になり,それ以外の染色体の構成のDSDsの女性(female)・男性(male)が,まるで「中性」「その他」のように排除されていったというのが実際だったのです。

ターナー症候群女性をはじめとするDSDsを持つ女性・男性に対して,「性同一性」という概念が適用されたのも,「体は女性(female)・男性(male)とは言えないのに,自分を女性・男性だと思い込んでいる」という,差別的な思考があったわけです。

もちろんトランスジェンダーのみなさんにとっては変わらず「性同一性・性自認」の概念は重要で,その尊重は大切なことです。
ですが,DSDsのある人々に「性同一性・性自認」という概念を当てはめるのは,大きな間違いで,欧米のDSDs先端医療では,「性同一性・性自認」という概念はほとんど使われないようになっているのです。

ターナー症候群女性をはじめとするDSDsのある人々を「男女以外」であるかのようにした「社会的生物学固定観念」の強迫化については,リベラル系の学術誌『ジェンダー法研究第7号』に掲載いただいた論考で詳しく解説しています。
現在,下のリンクから無料でお読みいただけます!
無料パンフレット
「学校や教室でDSDsについて触れるには?」
現在,様々な学校でLGBTQなど性的マイノリティーの皆さんの「性の多様性」についての授業が行われるようになりました。それはとても喜ばしいことなのですが,大変残念ながら,時にDSDsについて古い誤った話が伝えられることによって,教室にいるDSDsを持つ子どもが不登校になってしまったケースが起きています。
DSDsの判明・説明後,特に思春期は重要な時期で,誤解や偏見に基づく横やりは当事者家族の命に関わりかねません。
性別欄の取り扱いも「男・女・その他」といった選択肢では,DSDsを持つ子どもたち・人々に二次的なトラウマを与えかねません。ではどうすればいいのか,パンフレットに記載しています。
皆さんには,ぜひこのパンフレットを周りの方とシェアいただき,DSDsの正確な知識の啓発にご協力いただければと願います。


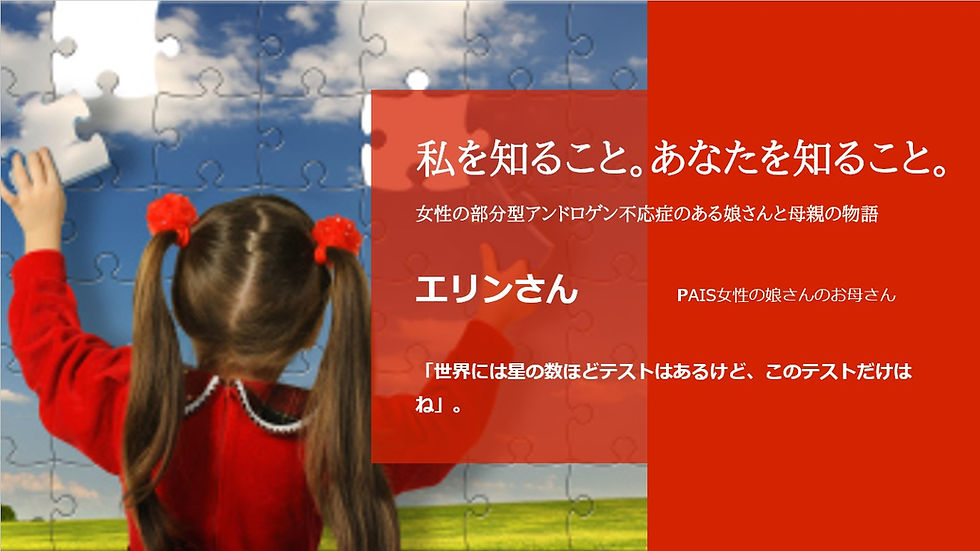
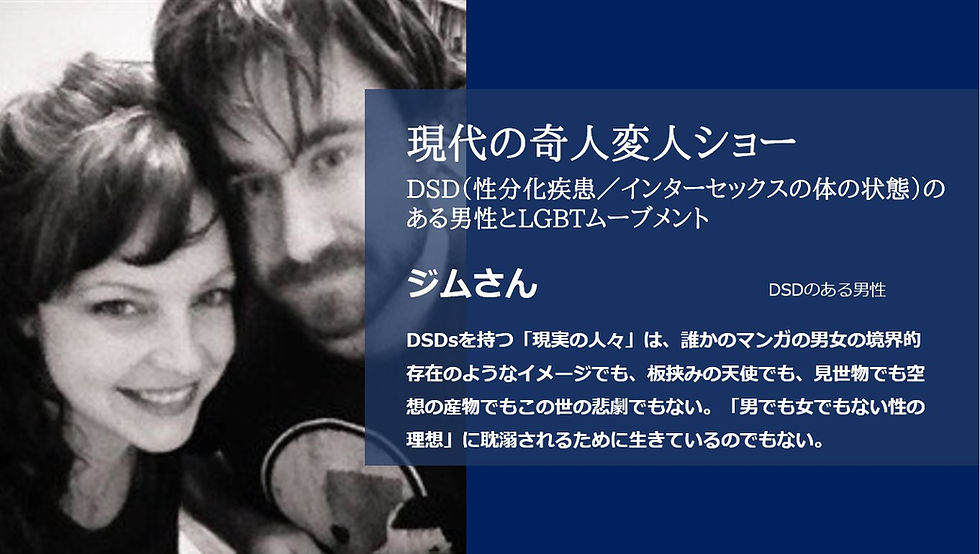
コメント